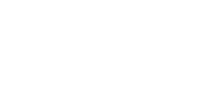- ご案内
- スケジュール
- 武者小路実篤
- 資料室
- ミュージアムショップ
作品鑑賞
「作品鑑賞」は、武者小路実篤の著作をわかりやすくご紹介するもので、
過去に館報『美愛眞』に掲載されたものを、再編集し掲載しております。
*日程や名称、執筆者の肩書きは、発行時のものです。
館報『美愛眞』6号 より2004年3月31日発行
小説「土地」
新しき村の誕生を描く作品

自分は一九一八年十二月の或日朝早く川岸に出た。清い川の流れは岩にぶつかり、泡を立てゝ流れてゐる。ある岸の岩の上に自分は立つた。自分は顔を洗ひ、うがいをつかつた。そして川向ふのじょう
「土地」の冒頭です。一一月一四日に新しき村の土地が決まってから、数週間が過ぎました。ある朝、川の向こう岸に見えるその土地を見ながら、「自分」は新しき村の成功を祈っています。「自分」は作者武者小路実篤と考えていいでしょう。実篤と仲間たちが新天地を求めて九月下旬に東京を出発してから、新しき村の土地が決まり、開墾の日々に至るまでが描かれた小説が「土地」です。一九二〇年二月に書き上げられ、その四月に雑誌『解放』に掲載されました。
日向に見つけた別天地
実篤は土地を見る前に、新しき村を
困難だった土地探しの旅
「土地」を読むと、理想を実現する熱意に燃えた彼らの意志の強さと行動力に驚かされます。当時、九州の東側を南下する鉄道は未整備でしたから、実篤一行は船を使って日向入りしました。日向に入ってからは、船・鉄道・馬車・人力車などを使いながらも、多くは歩いて、休むことなく精力的に土地を探し求めました。二六章には「自分は一月以上歩くことを修業した。(略)今は十何里の山道を歩くことはさう苦しくはなくなった」とあります。一日に数十キロも歩く日々が一か月以上も続いたのです。
土地探しの旅には、精神的なストレスも多くあったはずです。土地は経済的打算や権力関係が直接に反映するものです。土地を購入するための交渉相手である地主や郡長・村長は冷たい態度をとったり、土地の有力者の思惑や警察の注意によるのか、不自然に態度を変化させたりしました。
人々と触れ合い成長する実篤
友から離れ、知り合ったばかりの仲間と一緒におこなう旅の途上で、冷たい現実に何度も触れました。しかし、実篤は現実的な経験を積みながらも、困難に負けず、仲間とそして日向の人々と、さらに真心をもって付き合おうとします。
点数の厳しい評論家である
一七章の孤児院を訪問する文章の中に、次のような一節があります。
自分はこの仕事を始めようと思つてから、地上に人間の費やした労働のつみ重なりを今更に注意して驚くことが多かつた。何を見ても人間の精神と肉体の働きの積み重なりを語らないものがないのに驚いた。それは不可能に見えることをちやんと実現してゐる。
新しき村をはじめるまで、ゲーテやゴッホのような天才たちと並ぶ存在になることをしきりに求めていた実篤は、現実世界の中での経験を通して、無名の人たちの努力によって成し遂げられるものへの敬意を語るようになったのです。
祈り
神よ。自分は心で神に礼拝した。自分の目は涙ぐんでゐた。清き流れはたえず流れ、仲間を受入れて海へと流れてゆく。/幸よあれ!
これが末尾の文章です。二章から、土地を手に入れるまでの経緯を書きつづったあと、最後の三四章・三五章で再び一九一八年一二月の早朝に戻ってきました。
仲間とともに苦労の末に手に入れた土地を見ながら、感謝の涙は清流のイメージにつながり、支流と一緒になって海へと流れてゆく川は、自分をふくめた新しき村の仲間が一つになって人類の意志を実現するイメージにつながっているようです。ここに実篤の祈りがこめられています。この一節は、実篤が書いた多くの文章の中で、最も美しいものの一つだと思います。
(瀧田浩 二松学舎大学講師)
バックナンバーはこちら >>